こんにちは、まこ(別名:おみそ先生)です。
現役小学校教員で2児の母をしながら、
味噌づくりを通して“私たちと地球の未来を考える活動家“
として日々発信しています。
前編でのおさらいと、後編で伝えたいこと

前編にあたる、
「子どもが真の成長を遂げる為に必要な自己肯定感の育み方。」
では、現代の子どもたちの自己肯定感が低い背景として、
核家族化や共働き世帯の増加、
そしてSNSの発達によって「周りの目を気にする」
という状況を挙げました。
また、自己肯定感を高めるためには、
外側の自分を大きくすることではなく、
内側の自分を受け入れることが重要である と述べました。
後編では、自己肯定感を高めるために、
自己一致感という概念に注目し、
具体的な行動や親の関わり方について深掘りしていきます。
自己一致感とは?

自己一致感とは、
自分が思っている自分と、実際の自分との間に
大きなギャップがない状態、
つまり「ありのままの自分」を
受け入れられている感覚のことです。
自己肯定感が「どんな自分も自分らしくていい」という
自己評価であるのに対し、
自己一致感は「私は私らしく生きている」という
自己認識です。
なぜ自己一致感が重要なのか?
自己一致感が高い人は、
- 自分のことをよく理解しているため、
無理なく自分らしく行動できる - 周囲との関係性が良好になりやすく、
孤独を感じにくい - ストレスを感じにくく、心の安定が保たれる
- 変化を恐れず、新しいことに挑戦できやすい
という特徴を持っています。
自己肯定感は、自己一致感を土台にして育まれるものです。
自分とは何者で、何をしたいのかが分からない状態のまま
結果を出そうと努力をするのは、
砂場の上にタワーマンションを建てるようなものです。
小中学生の中でも、燃え尽き症候群かのごとく
頑張っていたのに急に動けなくなる子たちが見受けられますが、
外側の自分の成長にばかり意識が傾いていたり
外側の自分だけを周りの大人に評価されていたら
内側の自分が悲鳴をあげて
ある日突然、電池が切れてしまうようなことも
あって当然なのです。
子どもの自己一致感を高めるために親ができること

では、子どもの自己一致感とはどうやって育んでいくと
よいのでしょうか?
-
子どもがその日の出来事を振り返られる時間を作る
- 食卓の時間や寝る前のひと時など、
子どもの話を遮らずに聴く時間を作る - 聴く際は、共感の言葉や相槌を打つことで、
子どもが安心して話せる雰囲気を作る
- 食卓の時間や寝る前のひと時など、
-
子どもの気持ちを尊重する
- 子どもが好きなこと、興味のあることを尊重し、
それを否定せずに見守るようにする - 子どもが失敗した時にも、責めるのではなく、
励ましの言葉をかけるようにする
- 子どもが好きなこと、興味のあることを尊重し、
-
子どもの自主性を大切にする
- 小さなことでも自己決定のできる機会を与える
- 親が子どもの成長を待ち、失敗も含めて色々な経験を
できるようにさせる
-
親が自分の人生に夢中になっている姿を見せる
- 親が自分の使命を明確にしながら生きること
- 親が自分と向き合っている姿を子どもに見せる
-
家族で一緒に過ごす時間を大切にする
- 家族での会話を増やし、お互いの価値観をありのままに
話せる機会を設けるようにする
- 家族での会話を増やし、お互いの価値観をありのままに
まとめ

自己肯定感を高めるためには、自己一致感が不可欠です。
子どもの自己一致感を高めたいと思うならば、
親も自己一致感を感じながら生きていくことが必要です。
親がどう生きればいいのか分かっていない状態では、
子どもも無意識のうちに親に対して自己開示ができません。
親が自分の人生に夢中になっている背中は、
子どもにとって最高のお手本です。
子どもが、「私は私らしく生きていいんだ」と
感じられるような環境をつくりあげることで、
子どもは自己肯定感も育み、
健やかに成長していくことができるでしょう。
「大人の意識が変われば、子どもたちの歩む未来も変わる」
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

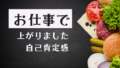

コメント