講演家&PCスキルアップアドバイザーの晴田です。
今日はボランティアのお話です。
ボランティア
ボランティアは
要するに無償で働く
というような意味だと思うのですが
ボランティアにボランティア精神は必要か
ということを考えた時期がありました。
そんな中で
今思えばアホや
と思うことがありまして
教員採用試験の小論文の課題が
学校教育の中で
ボランティア精神を身に付けさせるには
どうすれば良いか
というものでした。
これが悪い意味でタイムリーな課題で
そのちょっと前に
親友とボランティアについて語り合ったばかりだったのです。
結論としては
ボランティア精神など必要ない!
行動あるのみだ!
というものになりました
それでその主張そのままの論で
小論文を書き上げたわけです。
相手の求めるものをまったく無視した
自分勝手な内容ですので
当然不合格です笑
ですが若気の至りということで
まぁ良い経験だと思っています笑
疑問を抱くキッカケ
見方によっては
かなりひねくれた考えを抱くキッカケは
中学校1年生の時の道徳の授業でした。
その時の資料は
募金に関する内容でした。
要約すると
あるクラスで
募金についての話し合いがあり
募金をみんなでしたいから
1人100円にしよう!
という意見が出た。
それに対して
100円が嫌な人や
逆にもっと募金したい人がいるかもしれないので
一律にすることは良くないという意見が出て
話し合いがまとまらない。
最後に担任の先生が
「心のこもらない100円よりも
心のこもった10円の方が良い」
という話をしたところで
資料は終わりました。
この話に私は疑問を抱きました。
本当か?
「100円の方が10円よりも
役立つことは間違いない。
何よりも
そのお金に
心がこもっているかどうか
判断のしようがない。」
と思ったのです。
する側の論理
これは
ボランティア活動に
ボランティア精神が必要か
ということにもつながります。
結局のところ
重要なのは
される側であって
する側ではないのです。
こういう場合に
なぜかする側の論理になってしまい
だからこそ
ボランティア精神がいるかいらないか
というズレた話になってきます。
極端な話
先ほどの募金の例で言えば
もらう側としては
金額が大きい方が良いに決まっているのです。
例え見栄っ張りで入れた1000円でも
100円よりも役立つのです。
過程の話になりますが
イヤイヤながら活動していても
それを態度に出さずに
本当に役立つ活動をしていたとすれば
やる気満々で空回りしている人よりも
される側としては役に立つわけです。
つまり
偽善でも役立つなら
それはやらないよりよっぽど良いのです。
される側の論理こそ重要だと思います。
ボランティア精神とは何か
ではそのボランティア精神とは何なのかですが
ようするに
報酬を物や金銭などの物質に求めない性質
ではないかと思います。
感謝の気持ちやお礼の言葉はもちろん
自己有用感や自己肯定感が
報酬として成り立つのです。
それがボランティア精神だと考えます。
もしも本当に
それすらも求めないならば
それはボランティア精神を超えて
愛そのものになります。
まとめ
募金やボランティア活動など
について語られるとき
される側が置き去りにされて
する側の論理の話になることがありますが
それは視点自体がズレていて
大事なのは
される側についての話なのではないかなと
私は思うのです。
今日もありがとうございました。


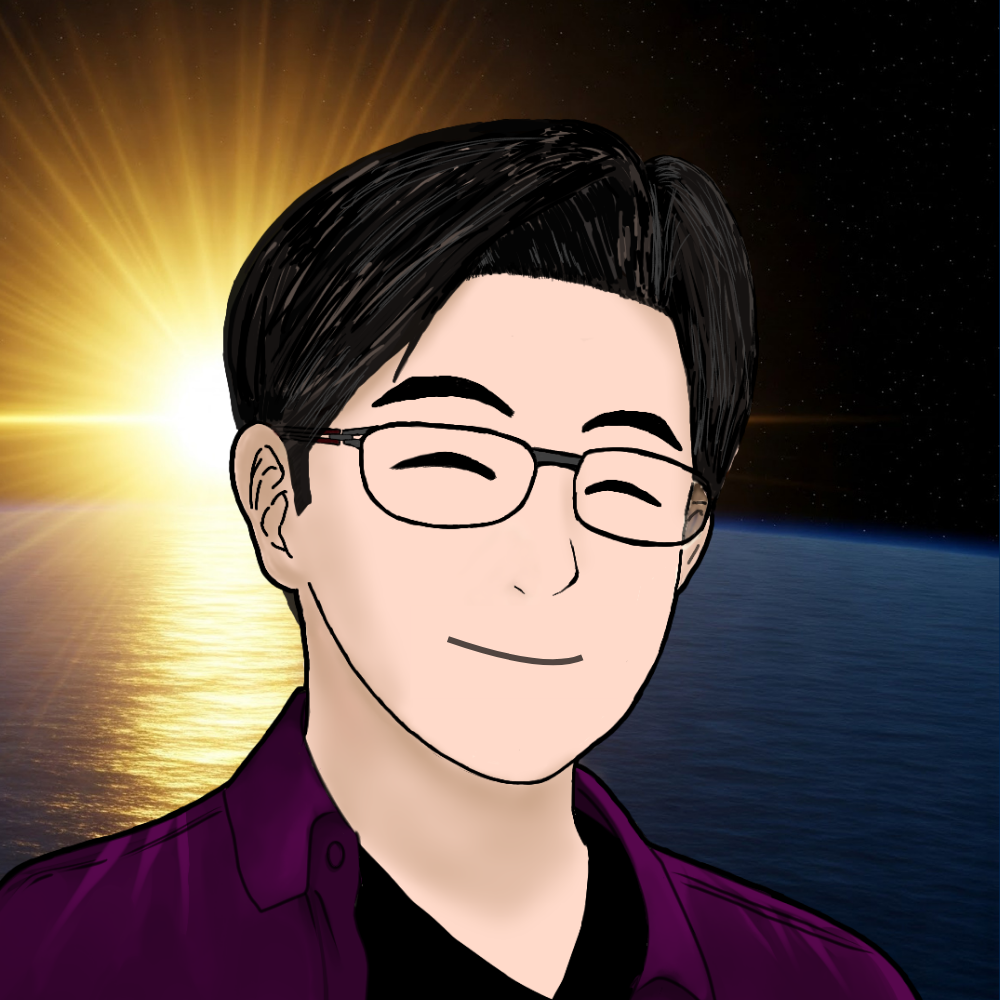


コメント